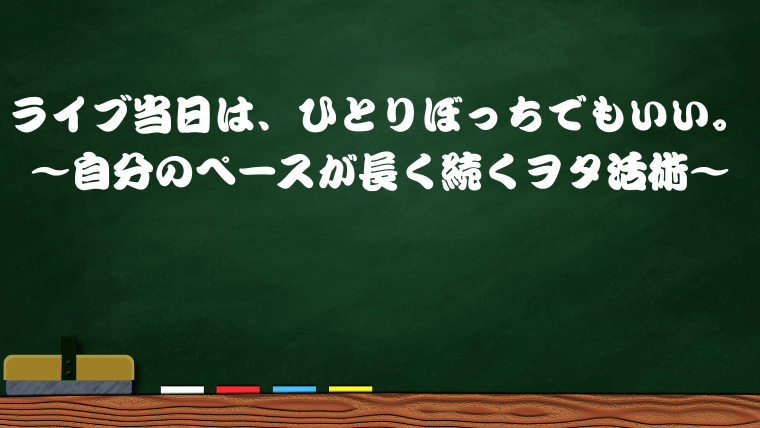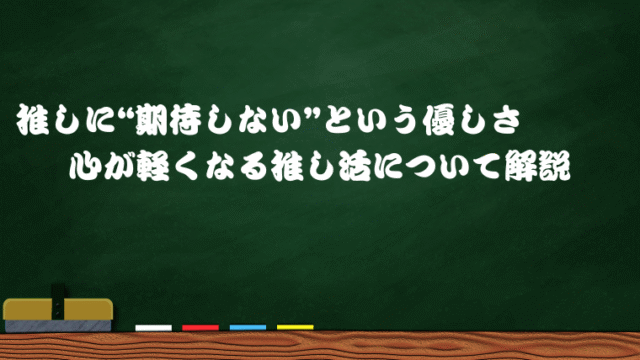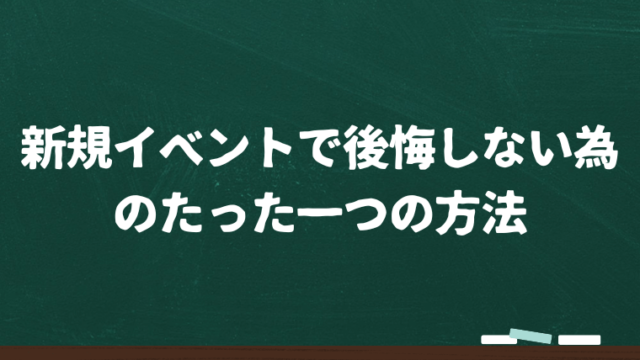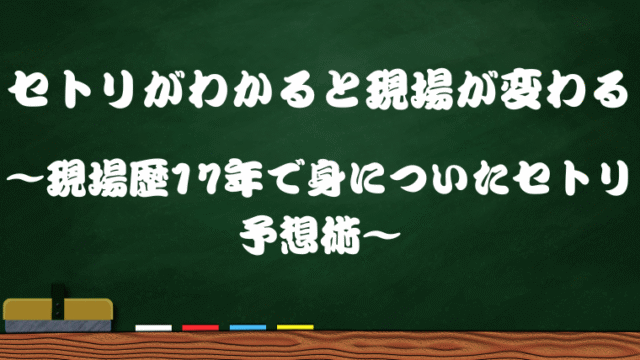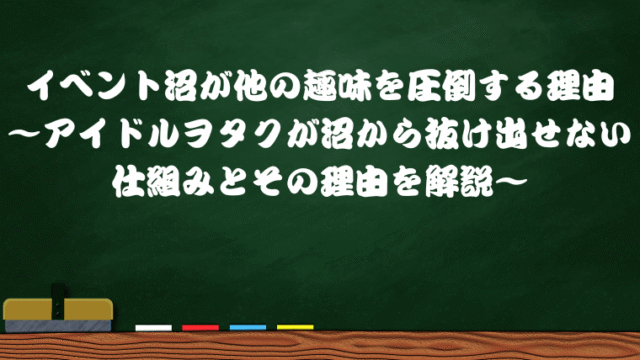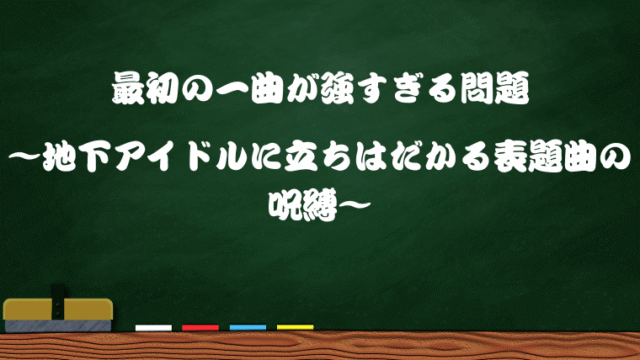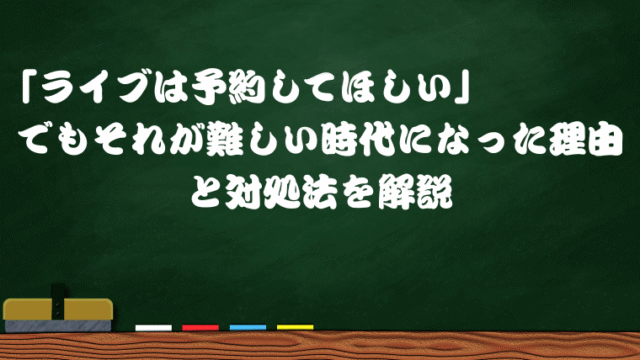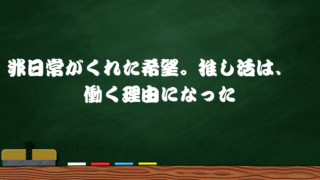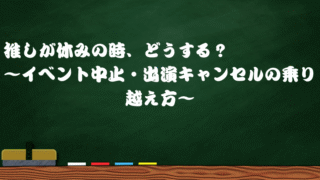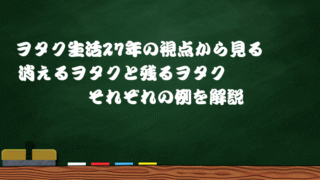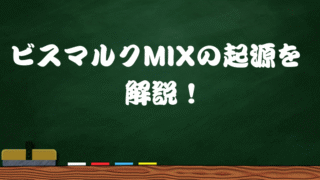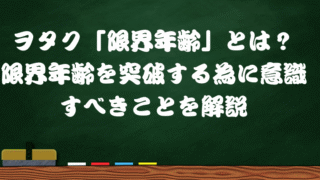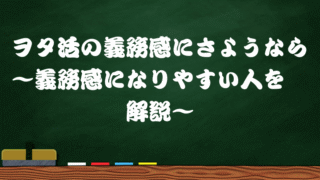はじめに
「ライブに一人で行くのは寂しいですか?」
「知り合いがいないと浮きますか?」
SNSなどで、こうした質問を見かけることがあります。
ライブやイベントというのは、誰かと一緒に行ったほうが楽しい――そんな風に思われがちですが、長年現場に通ってきた今では、むしろ「ひとりで行くスタイル」の方が、精神的にラクで、自分に合っていたと感じています。
今回は、「ひとり参戦」の魅力と、それがいかにヲタクとして長く活動を続けるための秘訣になりうるのかについて、自分の体験も交えながらお話ししたいと思います。
ファン同士の“群れ”は、時に寿命を縮める
ライブ会場に行くと、グループでわいわい話しながら行動しているファンの姿をよく見かけます。打ち上げや現場終わりのご飯、会場外での待機時間など、仲間と一緒に盛り上がることも、確かにライブの楽しさの一つかもしれません。
しかし、無理にグループで行動し続けることには、実は思わぬ落とし穴があります。
たとえば―
本当はこの現場に行きたいのに、仲間の意見に合わせて別のイベントへ。
今日のパフォーマンスには少し冷めていたけど、周りが盛り上がっているから無理して盛り上がるフリをしてしまった。
仲間内で推しが被って微妙な空気に。
こうした“合わせる疲れ”は、確実に心に蓄積していきます。最初は楽しくても、徐々に「しんどいな」「気を使うな」と感じるようになり、最終的には現場そのものから離れてしまう人を何人も見てきました。
無理にファン同士で行動している人ほど、早く“燃え尽きる”傾向があるのは、こうした理由によるものです。
自分なりの“暇つぶし”を持つこと
一人での現場参加を快適にするためには、「待ち時間の過ごし方」が非常に大切です。
ライブやイベントでは、整列や開場前などに1~2時間ほど待つことが珍しくありません。その間、何もすることがないと、つい周りのグループに目が行って「やっぱり一人って寂しいな…」という気分になってしまいがちです。
そこで、自分が普段取り入れているのが、以下のような“暇つぶし習慣”です。
読みかけの本を持っていく
今期アニメをサブスクでダウンロードしておく
X(旧Twitter)で過去のライブレポを読み返す
会場周辺を少し散策する
こうした「ひとりでも楽しめるコンテンツ」を持っておくと、現場がより気楽な空間になります。
特に最近は、現場の合間に読書やカフェ巡りを楽しむ“ソロ活ヲタク”も増えており、自分の世界を大切にするスタイルが少しずつ市民権を得てきていると感じます。
名前も知らぬヲタクと一瞬の連帯を楽しむ
ひとり参戦だからといって、孤独なわけではありません。
現場で隣にいる見知らぬヲタクと、同じ楽曲で高まり、一緒にコールやフリコピをして盛り上がる―そんな“一瞬の連帯感”は、グループで行動しているとき以上に強く感じることもあります。
特にコールが揃った瞬間、視線がふと合って頷き合う。終演後、「あの曲ヤバかったですね!」と軽く言葉を交わす。それだけで、「今日この現場に来てよかった」と心から思えるのです。
名前も知らない、SNSでも繋がっていない。けれど、今日この瞬間を共にした“仲間”であることには違いない。
この距離感こそ、ひとり参戦の醍醐味だと思っています。
自分のペースを守ることが、長く続ける秘訣
ヲタ活を10年以上続けていると、「どうしたらこんなに続けられるんですか?」と聞かれることがあります。
答えはとてもシンプルです。
無理をしないこと。そして、自分なりの目標を持つことです。
現場に行きたい時間に参加し、疲れている日は午前中は休む。全力でヲタ芸を打ち、現場で仲間と合流し一緒に盛り上がる。気が向く現場があればひとりでフラッと参戦する。
そんな「自分のペース」を大切にしてきたからこそ、ここまで続けてこられたのだと思います。
一人で行動することは、自由であると同時に責任も伴います。だからこそ、自分の気持ちに正直に、無理のない範囲で動けるのです。
おわりに
ライブやイベントは、本来“自由に楽しむ場”であるはずです。
それなのに、「ひとりだから」「仲間がいないから」という理由で躊躇してしまうのは、とてももったいないことだと感じます。
無理に合わせる必要はありません。誰かのペースに付き合う必要もありません。自分のペースで、自分の気持ちが動いたタイミングで動く。それこそが、長くヲタ活を続けていくための秘訣です。
たとえその日が“ひとりぼっち”だったとしても、楽曲で一緒に湧いた誰かと視線を交わし、軽く「またどこかで」と挨拶できたなら、それで十分素敵な一日です。
「ライブ当日は、ひとりぼっちでもいい。」
その言葉を胸に、これからも自分のスタイルで、推し活を楽しんでいきましょう。今回も最後までご覧頂きありがとうございました。